 妙好人
妙好人 第91回 東悦子さん 下
永代経の全体座談で、悟朗先生に手を挙げ、「グズグズしとって、一歩も踏み出せません」と言うと、先生は「グズグズしながらでも、飛び込んだらどう?」と応えられ、20分ほど、悦子さんに対してお話しをされます。先生は「手紙を読んで嬉しかった。泣きたか...
 妙好人
妙好人  妙好人
妙好人  妙好人
妙好人  妙好人
妙好人  妙好人
妙好人  妙好人
妙好人 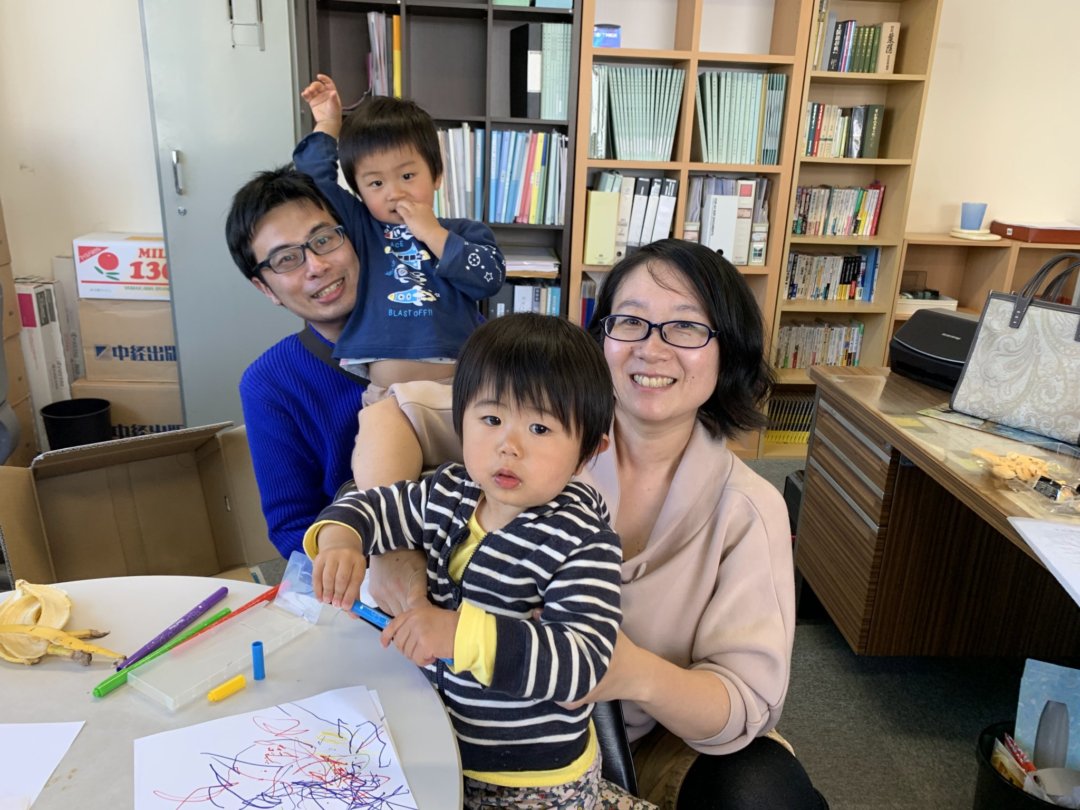 妙好人
妙好人  妙好人
妙好人 .jpg) 妙好人
妙好人  妙好人
妙好人