 妙好人
妙好人 VOL.138 生死出づべき道 第18回 庄松同行 その4
さて、庄松さんの話に戻しますと、ご門主は喜ばれ、「お前は正直な男じゃ、今日は兄弟の杯をするずよ」と召使いの者を呼び、お酒を取り寄せご門主のお酌で、ご馳走になります。それ以降、ご門主の御前に通られるようになります。しかし、この世のことはすぐに...
 妙好人
妙好人  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道 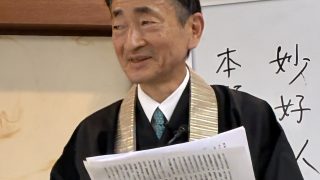 生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道  生死出づべき道
生死出づべき道